LST-FiとLRT-Fiの台頭
本モジュールでは、LRTがDeFiプロトコル内でどのように利用されているかを解説します。実例としては、イールドボールトの活用、レバレッジド・ステーキング、LRTを担保としたステーブルコイン、リハイポセケーションなど、多様なユースケースを取り上げます。具体的なプラットフォームとして、Pendle、Gearbox、Prisma、Ethenaが挙げられます。本セクションでは、LRTがこれらのシステム全体をどのように流通し、新しい利回り獲得手段や複数層のリターン、コンポーザビリティおよびレバレッジの新たな形を実現しているかに重点を置いて説明します。
LST-FiおよびLRT-Fiの定義
LST-Fiは、LST(流動性を維持したままステーキングされたETHやその他の資産を表すトークン)を活用した金融活動を指します。これらのトークンは、ステーキング報酬を受け取りつつ、資産のアンステークを必要とせずにDeFiプロトコルで利用できます。当初はstETHのレンディングプールや流動性ファームへの預入といったシンプルな用途が中心でしたが、現在ではLSTを担保やステーブルコイン発行の基礎資産、利回り戦略の中核とする多様なエコシステムへと進化しています。
対してLRT-Fiは、LST-Fiを基盤にリステーキングのロジックを加えた新しいカテゴリです。LRTは、ベースレイヤーのステーキング報酬を得るだけでなく、EigenLayerなどのリステーキングプロトコルを通じて追加の分散型サービスのセキュリティも担うため、LSTより複雑な仕組みとなっています。LRT-Fiでは、AVS手数料やEigenLayerポイントなどリステーキング固有の報酬メカニズムが、従来のDeFi利回りファーミングに重層的に統合されます。これにより、1つのトークンが運用方法に応じて同時に三つ以上の報酬を受け取れる、多層的な戦略が可能となります。
この違いは、異なるリスクプロファイルや報酬源を定義するため重要です。LST-Fiは主にEthereumのコンセンサスレベルのリスクを扱いますが、LRT-Fiはアクティブバリデーションサービスやリステーキング契約によるアプリケーションレイヤーのリスクを伴います。そのため、両者は高いコンポーザビリティを共有しつつも、ユーザーやプロトコルにおいて異なる資産クラスとして認識されています。
DeFiにおけるLSTとLRTの活用法
LSTは、予測可能な利回りや低ボラティリティ、市場からの高い需要により、レンディングやトレーディングプロトコルで長らく統合されています。AaveやCompoundではstETHやrETHが担保として受け入れられ、CurveやBalancerではLSTベースの流動性プールによってLST、ETH、ステーブルコイン間のスワップが可能です。これにより、ユーザーはステーキング資産を売却せずに流動性を確保し、同時にステーキング報酬を享受できます。
LRTも同様の方法で採用が進んでいます。たとえば、RenzoのezETHやEther.fiのeETHは、GearboxやMorphoといったマネーマーケットに預け入れることで、利用者はステーブルコインの借入やレバレッジ運用ができます。Pendleでは、LRTを元本トークンと利回りトークンに分割し、将来のリステーキング報酬取引や固定利回り戦略の構築を実現しています。さらに、AVS報酬の予測性によってLRT担保100%のステーブルコインを発行するプロトコルも登場しています。
こうした事例は、DeFiにおいてパッシブなステーキング資産がアクティブで生産的な金融商品へと変わる大きな流れを示しています。追加利回り層と高いコンポーザビリティによって、LSTとLRTはいずれもモジュラー型利回りポートフォリオ構築の要となっています。
ケーススタディおよびプロトコル例
Pendle
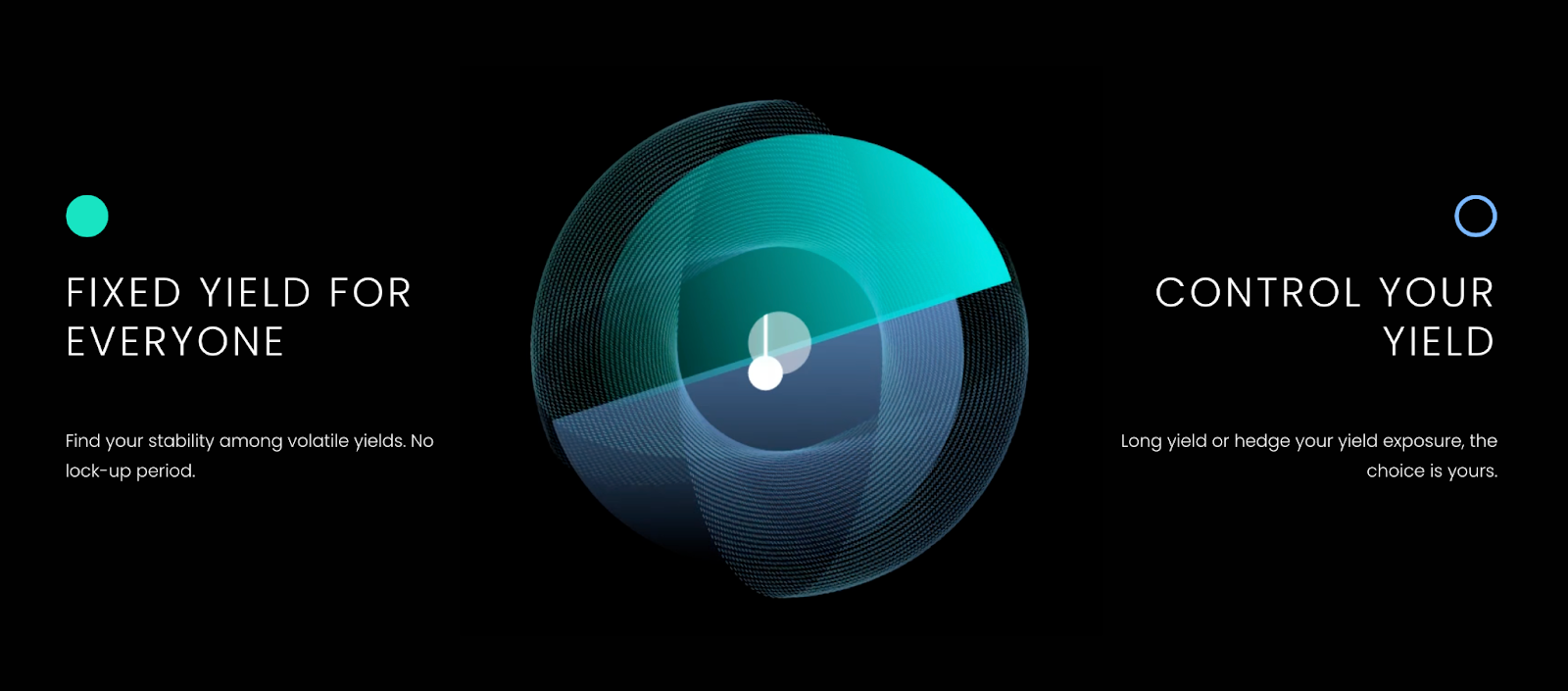
Pendleは、最も活発なLRT-Fiのプラットフォームの一つです。ユーザーはLRTを預け入れ、元本トークン(PT)と利回りトークン(YT)という2つの資産に分割できます。PTはLRTの基礎価値を表し、ゼロクーポン債のように取引可能です。YTは将来のリステーキング報酬やAVS手数料に対応しており、この構造によって固定利回りファーミングや報酬の投機的取引、利回りヘッジなど先進的な運用が可能となります。
Gearbox

Gearboxは、LRTをレバレッジクレジットアカウントと統合することで、ユーザーがリステークETHへのエクスポージャーを維持しながら、借りたステーブルコインでインセンティブをファーミングできる仕組みを提供します。たとえば、ezETHを預けUSDCを借り入れ、両方の資産で運用することで、ステーキング・リステーキング・DeFi報酬を複利で積み上げるリスク調整型ポートフォリオを構築できます。
Prisma Finance
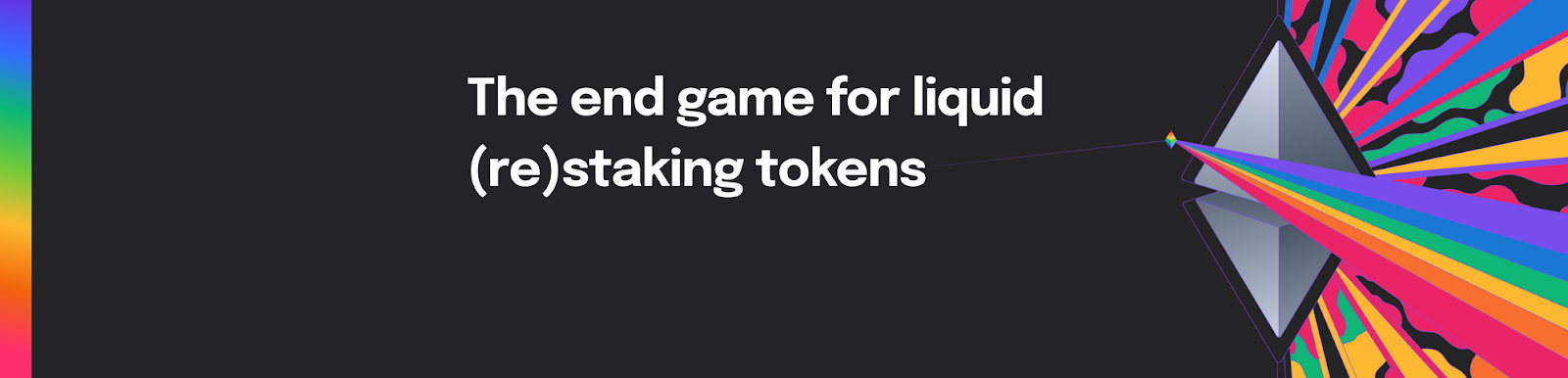
Prisma Financeは、LRTを担保にステーブルコインを発行できるモデルを導入しています。これは、ETHやLST担保でDAIを発行するMakerDAOのモデルに近いものです。このスキームによりLRTの活用範囲がステーブルコイン市場まで広がり、リステーク資産が分散型流動性の基礎となります。
Kelp DAOやSwellなども、LRT発行時にネイティブなDeFi統合を実装しています。これらの連携により、ユーザーはトークンを自動でステーキング・リステーキングし、選別DeFiボールトやインデックス商品へ投入でき、効率的な利回り集約パイプラインが実現します。
Ether.fiの「Mint • Spend • Earn」キャンペーンは、LRT-Fiを一般ユーザー向けに展開する事例です。リステークETH担保のプリペイドカードを発行しつつ、ステーキングやEigenLayer報酬も得られる仕組みであり、LRT-Fi戦略が資本市場だけでなく消費者向け金融にも活用できることを示しています。
リワード積層とDeFiメタ
LRT-Fi人気の根幹にはリワード積層があります。標準的なLRT-Fiポジションでは、Ethereumのステーキング報酬、EigenLayerのAVSインセンティブ、LRT発行主体のポイントやエアドロップが得られます。加えて、これらのトークンをDeFiプロトコルに預けることで、プロトコル独自の報酬や利息、ファーミングインセンティブも受け取ることが可能です。
こうした複利効果により、プロトコルのポイントキャンペーンやレトロアクティブ報酬制度が加わると、極めて高い利回りポテンシャルが生まれます。例えば、ezETHをPendleに預け入れると、Renzoポイント・Pendleポイント・EigenLayerポイント・取引手数料などが同時並行的に獲得できます。
この構造は、リステーキング利回り最大化を軸とする新DeFiメタを創出しました。高利回り戦略でユーザーコミュニティが形成され、多トークン報酬をトラッキングする新フロントエンドが登場、リスク評価も単一トークンから複合ポジションへと進化しています。
その一方、利回り積層はリスク構造の複雑化も招いています。ユーザーは複数階層のスマートコントラクトリスク、プロトコルガバナンス変更、AVSによるスラッシュ等に晒されます。利回り最大化に向けては、流動性・コンポーザビリティ・ボラティリティの適切な管理が不可欠です。
流動性、リスク、インフラギャップ
LRT-Fiは急成長を遂げていますが、インフラ面ではまだ課題も多い新興セクターです。流動性の分散は依然として課題であり、各LRTが発行主体やバリデータセットに紐づくため、二次市場の厚みに欠け、既存のLSTと比べて取引機会や同種LRT間の価格差が生じやすい傾向があります。
リスクモデルの確立も大きな課題です。LRTはリステーキングに伴いEigenLayerのAVSによるスラッシュリスクを抱えます。多くのDeFiプロトコルはLRTを高格付け担保とみなしていますが、スラッシュやAVS障害発生時の対応策を有する事例はごく少数です。同一LRTを複数プロトコルが一斉に統合した際、システミックリスクが発生する懸念もあります。
インターオペラビリティも発展途上です。LRTは現在Ethereumメインネットに限定され、Symbioticのようなクロスチェーン展開も一部見られますが、LRT-Fiの多くは依然サイロ化した状態です。他チェーンやロールアップへのブリッジには、オラクル依存やガバナンス分断といった新たな課題が発生します。
さらに、バリデータ行動やリステーキング戦略の透明性も限定的です。多くのプロトコルがダッシュボードや報酬内訳を提供しますが、ユーザーが自身の資本がどのAVSにどのように割り当てられているかやリスク内容を十分把握できていないケースがみられます。将来的な成長には、レポート標準化・バリデータスコアリング・AVS情報開示の徹底が不可欠です。





